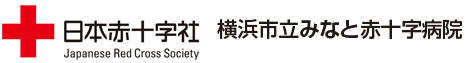2023/3/24
こんにちは、5AKです。
当院において総合防災訓練が開催されたので、その様子をご報告します。
この訓練は2部構成になっています。
第1部は6C病棟での地震後に汚物室からの出火という設定で防災訓練が実施され、第2部は大規模う災害が起こった後に、多数傷病者を受け入れる訓練になっています。
コロナ禍で3年ぶりの開催となり、看護師は64名の参加、他に医師、コメディカルスタッフなど多数の職員が参加されました。院外からも赤十字ボランティア、赤十字奉仕団、実習校の看護学生が傷病者役、ボランティア役として参加してくださいました。ご協力いただきました皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。
その中で、黄色エリアのリーダー務めたYさんに感想を聞いてみました。
「病棟部署単位で行う災害訓練とは異なり、病院周辺の地域やボランティアの方々と共に、大規模災害が発生した際の対応訓練を行いました。多数の負傷者を一気に受け入れるとなったとき、医師をはじめ看護師や事務、検査などの様々な職種が連携を密にとり、対応していかなくてはならないことを実感しました。そのほかに、平常時から他職種との連携をとり、顔の見える関係性を築いていく事も、いざ大規模災害が発生した時には必要であると思いました。エリアリーダーとしては、負傷者のみならず、救護活動を行っている職員のケアも重要な役割だと疑似体験できました。いつ起こるかわからない災害に、しっかり備えていきたいと改めて考えさせられました。」
また、訓練前にJSPEEDや災害診療録、トリアージについて動画配信にて事前研修を行いましたが、訓練参加者は、いざという時のために事前訓練は実施した方がいいと100%の方が思っていました。
全員が訓練に参加できることはなかなかないので、順次参加できるよう部署内で調整を図り、また事前訓練として動画視聴を見ていただくことも大切な研修ととらえて参加していただければと思っています。
今後も「災害はいつでもどこでも起きる」に常時備えていきたいです。
2022/12/26
5A 病棟 Kです。
先日行われた第2ブロック支部総合訓練の様子をお伝えします。
日本赤十字社は全国を7つのブロックに分けてブロック単位ごとに救護体制を敷いています。
神奈川県は関東1都6県と山梨県、新潟県を1つの区域とした第2ブロックに所属しています。神奈川県では対応できない大規模災害が発生した場合に、県境を跨いだ協力体制が必要になるため、このような訓練が毎年開催されています。
今年度は神奈川県が担当となり、秦野市、神奈川県庁、平塚保健所、多数のボランティアさんなどにもご参加いただき市内の小学校に想定された避難所を巡回し、問題点の抽出とその対応について考え、調整を図る訓練となりました。
当院からは、救護班1班、その構成は、医師1名、看護師長(係長)1名、看護師2名、主事2名と訓練支援者として医師2名、看護師長2名、コメディカル4名の職員が派遣されました。
訓練は2日間にわたり開催されました。1日目は、チームビルディングに始まり、2か所の避難所を回りながら避難所アセスメントの実際の訓練です。
1か所目の小学校では他施設の救護班と協働し、感染対策をしながら、避難所の責任者などに情報収集し、避難者の情報収集を行っていきました。しかし、初めて使用する災害診療記録やJSPEEDの記録に翻弄され、総合的なアセスメントまでには至らず、反省点も多く抽出され、移動の中でその点について振り返り、2回目の避難所へ向かうこととなりました。
2か所目は、多職種で意見交換を行ったことで、2人1組となり、ローラー作戦ですべての傷病者に対応し、急変された避難者の対応、その後の搬送にまでつなげることが出来ました。また車で避難している方の情報収集とその方の体調にまで気づかい、避難所のハード面まで総合的にアセスメントすることが出来たようでした。
実動訓練の翌日は、グループワークでどのような点に配慮し、2回目をどのように動いたか、振り返りしながら、さらに自分たちの役割を考える機会となり、今後の実動に向けた課題も見出すことが出来たとおもいます。
このような訓練を繰り返し、有事に備え、準備をすすめていきたいと思います。また、有事の際はより連携強化が求められるため、平時から、赤十字施設間での顔の見える関係づくりを積極的に進めていきたいと思います。
2022/8/19
災害看護研修担当の5A Kです。
今回は、先日開催された救護員として赤十字看護師フォロアップ研修が開催されたのでその様子をお伝えします。
この研修は、救護員として登録されたスタッフ、実践者ラダーレベルⅡ以上の方が受講されており、秦野赤十字病院との合同開催となっています。
以前は、急性期医療対応ニーズを中心とした研修が主でした。しかし災害が多様化しており、災害の全サイクルに対応出来るよう研修内容が改訂されました。
特に地域アセスメント、避難所での災害関連死を予防するための公衆衛生や感染管理、要配慮者やグローバルヘルスの視点での災害看護ケア、原子力災害・被ばく医療、亡くなられた方やその遺族ケア、他機関との連携などが盛り込まれました。
この研修は前年の災害で得られた課題をもとに年々更新されてきており、実技では病院業務支援を学び、支援だけではなく受援にも目を向けた内容となっています。
受講生は、研修に参加し以下の学び、感想を述べられていました。
災害救護の原則はCSCATTTであり、それに則って救護の準備や災害時の行動を検討する必要がある事を改めて復習されてました。また、災害救護及び病院業務支援の原則は被災者の自立支援である事の重要性を学ばれていました。特に病院業務支援の演習では、日々のリリーフでも有効活用できるとの振り返りや被災地のニーズは様々でそのニーズも災害のサイクルに応じて容易に変化するため、支援内容を柔軟に考えて対応する能力や心構えが必要と気づかれたようでした。さらに、救護班として活動する前にまずは平時からの備えとして自身の業務の仕方や心構えを見直すきっかけとなったっ方もいたようでした。
まだ参加されていないスタッフや今後救護員として活躍されたい方は、このフォロアップ研修受講をお勧めします。
2022/8/4
災害看護研修担当の5A Kです。
先月、救護員として赤十字看護師養成研修が行われました。
私達赤十字看護師は、赤十字医療施設に看護師として3年以上勤務し、一定の救護教育と訓練を受け救護員として登録されます。
そのためにこの研修においてはラダーレベルⅡを目指すものが主として受講されています。
研修は、座学と実技を行い、以下の感想や学びを得られていたのでお伝えします。
座学では、赤十字の歴史、赤十字の救護活動、救護員としての役割について学びを深め、グループワークを通して日々の看護実践の学びを復習し、様々な病棟で勤務しているスタッフ間での知識を持って意見交換することで、より知識を深められていたようでした。
また実技では、トリアージ、担架搬送、救護所設営などを行い、実際の訓練に沿った考え方を学び、様々な視点で考える同じチームの意見を大切にしチームとして考える大切さとチームビルディングの重要性に気付かれていました。
現在、災害はいつでもどこでも起きる時代となっており、私たちは常にその準備をしておかなければならない重要性にも気づく事ができていました。
被災者にとって、何が重要かを考えながら、赤十字看護師としてこれからも研修、訓練を続けていきたいと思います。
2022/1/29
こんにちは!7D病棟ブログ担当のMです。
先日、赤十字救護看護師養成研修を受講したので研修の内容を紹介します!
災害が発生した際、赤十字は救護員を派遣し救護活動を行っています。赤十字救護看護師養成研修は、救護員となるために受ける必要のある研修の1つです。研修では、赤十字の歴史・救護活動の実績などについての講義、救護所テントの設営や担架の使用方法などについての演習がありました。
講義では、実際に救護員として活動した講師から話を聞くことができたので、とても貴重な機会でした!
演習では実際に救護所テントを設営しました!グループに分かれて、救護員のメンバーがどのように動くのか、物品の設置場所、被災者の動線などを考え、発表を行いました。実際に設営を行うことで、イメージがしやすかったです。
写真は、担架を使っているところと救護所テントの写真です。