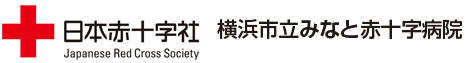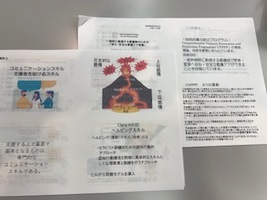2023/2/6
こんにちは!6C病棟のIです。
本格的に冬の季節となり、私は毎朝寒さと格闘する日々が続いているところですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、今回は泌尿器科がある6C病棟ではよくお世話になる、”排尿ケアチーム”についてお話しします。
当院には、医師や看護師、薬剤師、理学療法士等のスタッフが集まり、様々な症状を専門的にケアするための多職種チームがいくつか存在しており、その中の1つに排尿ケアチームがあります。
主な活動内容としては、膀胱留置カテーテルを1日でも早く抜去し尿路感染症を防ぐことや、カテーテル抜去後の排尿障害に対してのケア等を行い排尿自立の方向へ導くという活動をしています。
6C病棟に入院される泌尿器科の患者さんの中には、術後膀胱留置カテーテルをなかなか抜去することができない方や排尿障害が生じている方などがいらっしゃいます。
そのため、今後も日々の排尿状況等を確認し必要に応じて排尿ケアチームと連携を図ることで、患者さんが入院中だけでなく退院後も排尿を気にすることなく安心して過ごせるようなケアを行っていきたいと思います。
2023/2/2
こんにちは。6A病棟Tです。
当院では新卒看護師の教育支援としてプリセプターシップ制度が取り入れられており、新卒看護師(プリセプティー)1人に対してプリセプターが1人つきます。
今年6A病棟では6名のスタッフが新卒看護師のプリセプターとして活躍しています。その中の1人卒後4年目のKさんにインタビューしてみました。
・プリセプターになって10ヶ月が経ちますが、今の思いは?
→つい最近まで指導してもらっていた自分がプリセプターをできるのか不安でしたが、1年目スタッフと関わる中で自分も初心に返ったり、一緒に成長していけるような感じがしてやってよかったなと思います。
・プリセプターをやるにあたって研修や事前のサポートなどはどのようなものがあるんですか?
→実地指導者研修に参加します。そこでお互いの悩みや解決方法などを共有でき、自分たちの成長にもつながっているように感じます。また事前のサポートとしては、昨年プリセプターをしていた先輩からアドバイスをもらいながら、毎月教育目標を立てています!
・プリセプターをしてみて難しいこと悩むことはありますか?
→あります!笑
プリセプティーのスタッフ一人ひとり個性があって、関わり方を見出すのが難しいなと感じました。
・そのような時はどのように解決してますか?
毎月行っているプリセプター会で先輩たちを交えて話し合い、こんな関わりをしたらよかったというアドバイスをもらって、それを元に関わっています。周囲からの協力をもらうのが1番です。
プリセプターを中心に病棟のスタッフみんなで新卒看護師をサポートしてくれているのですね。
写真はある日の勤務中に撮影したプリセプター・プリセプティーの2人です。
写真からでも2人の素敵な関係性が伝わってきます。
2023/1/27
こんにちは。5A病棟の看護師Rです。
本日は、新型コロナウイルスへの感染対策を行いながら、退院支援に取り組み、オンライン面会を積極的に実施している5A病棟の様子をお伝えします。
現在、感染予防のため、原則として面会を禁止しています。コロナ禍になって以降、面会禁止となり、患者さんの入院した時の様子との差に大変驚かれる方もおり、言葉だけでは伝わりにくいことも多々あることに苦慮していました。
しかし、当院ではオンライン面会に取り組んでいます。具体的には、各病棟にタブレット端末が設置され、アプリケーションサービスを用いて、ビデオ通話を行っています。
ご家族だけでなくや関係機関の職員ともオンライン上で面会や認定調査、地域の観職員とともに退院前カンファレンスもしています。開始当初は、慣れない操作や機材のトラブルに右往左往していましたが、最近では、機械に強いスタッフの力を借りつつ、円滑に実施できるようになりました。
感染対策を踏まえ、IT技術を用いながら患者さんとご家族の不安に寄り添い、退院支援を引き続き行っていきます。
2023/1/26
外来のKです。
いつどこで起きてもおかしくない急変に対し、いち早く適切な対応ができるよう、毎年訓練を兼ねて勉強会を行なっています。容態の確認方法に始まり、人手や必要な物品を集めると同時に、迅速な心臓マッサージを行うなど、事例を元に一連の動きを復習しました。質の良い胸骨圧迫ができるよう、蘇生トレーニング人形を使用して手技をみんなで確認しました。頭では理解していても、いざという時には焦ってしまったり緊張したりと、なかなか頭や身体が動かないものです。日々いつ誰がどこで急変するかは予測不能なため、いかなる場合でも適切な対応ができるよう取り組んでいますが、初動のシュミレーションを繰り返し行うことで自信となることが事後アンケートで確認できました。
また、チームステップスの視点を取り入れて、より安全な医療を提供できるようにするため、事例でその場面をもりこみ、事後にチームステップスの4つの要素(リーダーシップ、状況モニター、相互支援、コミュニケーション)等も話し合いました。患者様が安心安全な医療を受けられるように、私たち医療者が医療チームとして個人のスキルをあげるのみでなく、「あれ?」と思う場面は声を掛け合い、双方で復唱確認することが重要だと実感し、チームステップスの視点が医療安全文化の醸成にとても直結していると改めて感じました。また、日頃のチーム医療の中でも、外来は他職種との連携で成り立っているので、チーム間での風通しの良い、声の掛け合いや連携が、患者様、職員間の安全につながることを実感できました。
2023/1/25
こんにちは、5A Tです。
今回は、外部から講師をお呼びして開催したCVPPP研修についてお伝えします。
CVPPPとは、包括的暴力防止プログラムの略で、シーブイトリプルピーと読みます。
主に精神科での対応として用いられますが、それを一般病院向けにアレンジした研修を、毎年開催しています。
とは言っても、感染症の拡大により3年ぶりの開催です。
このプログラムは「暴力防止」というフレーズから護身術の類いと間違われがちですが、「包括的」ということから「怒りのメカニズム」や怒りを静める「ディ・エスカレーション」への理解を大切にしています。
午前中は、講義を聞くことで理念を理解し、午後は怒りに対する関わりや、患者さんもスタッフも傷付かない対応の仕方を学ぶと共に、倫理的配慮についても考えるグループワークが行われました。
参加した看護師からは「今まで気付かなかった視点を教わり、目からウロコだった」「すぐに現場で活かしたい」など好評でした。日々の看護を振り返ると共に、患者さんの疾患だけでなく、背景や想い、感情などを包括的に考え、寄り添える看護を提供することに繋がるような研修になったと思います。