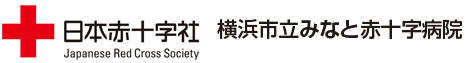2023/1/10
こんにちは6A病棟看護師のSです。
今回は6A病棟で活躍してるママさんナースにインタビューしました。
Q.仕事のやりがいはなんですか?
A.病棟は寝たきりの患者さんが多く、不調を自ら表現できる方も少ないです。そのため、自分で患者さんの状態をアセスメント・判断したり、そしてケアをするなど盛り沢山なので看護師としてのやりがいを感じます。仕事終わりに子供の保育園にお迎えに行き、子供が走り寄ってきてくれた時に、「頑張ってよかったな〜」と思います!
Q.仕事と家事を両立する工夫はなんですか?
A.保育園へのお迎えがあるので残業が難しいですが、快く病棟スタッフのみんなが手伝ってくれるので、甘えています。また、家事も家族と協力してやっています。職場や家族の理解があるので頑張ることができています。
Q.仕事をしている中での息抜きや楽しみはなにかありますか?
A.通勤や帰る時間の束の間の1人の時間に本を読むことと、お休みの日に子供と公園へ行って一緒に滑り台をしたり、砂場で山を作って遊ぶことです。
6A病棟には現在6名のパパ・ママさんナースが所属しています。家族と協力して仕事と家事を両立している姿が見られます。私もたまにお子さんの写真を見させてもらうことがあるのですが、とても笑顔が素敵でほっこりします。
仕事の中でもとても助けていただくことが多く、これからも病棟ではパパ・ママさんナースが働きやすい環境を作っていきたいですね!
2023/1/5
こんにちは、6C病棟のIです。
今回は6C病棟のクリスマスについてご紹介します。
6C病棟では毎年12月になると、デイルームにクリスマスツリーが出現します。
これは、入院中の患者さんが少しでも季節感を感じることができるようにという思いをこめて
新卒看護師さんたちが準備を行っています。
そのためクリスマスツリーの飾り付けには、その年の担当の色が出るので私たちスタッフは患者さんと一緒にこの期間を楽しんでいます。
またツリーだけではなく、病室の前にもクリスマスのイラストが貼られているため、デイルームまで足を運ぶことができない患者さんにも気分を味わっていただけるように工夫しています。
現在コロナ禍で面会制限もあることから、入院期間を退屈に過ごされる方も多くなってしまっていますが、その日々に少しでも楽しみが添えられていればいいなと思います。
2023/1/4
あけましておめでとうございます。
本年もナースのブログをよろしくお願いします。
7B病棟のWです。
先日、新卒看護師を対象に、「急変時アセスメント研修」が行われました。この研修では、講義や実技演習を通じて、“一次救命処置”というAED以外の特別な器具を使用せずに行う心肺蘇生法を中心に学習します。今回は、研修受講後の看護師に研修での学びや感想に聞いてみました。
Aさん
一連の処置をグループメンバーと何度も繰り返し練習する事で、救命処置が必要な場面で個々のメンバーが果たすべき役割の種類や、役割ごとに異なる救命処置の手技について学び、習得することができました。今後、救命処置に携わる機会があれば、研修で得た知識を生かして、私にできる役割を果たしながら積極的に医療チームと連携し、患者さんに迅速かつ的確な対応を行えるよう努めていきたいと思います。
Bさん
入職してすぐに急変の場面に立ち会った時は、自分は何をしたら良いのか分からず病室の外から先輩方の動きを見ていました。ですが、この経験があったからこそ、実際の現場をイメージしながら研修に臨むことができ、1年目の私でも物品準備や胸骨圧迫など患者さんのために行えることがあるのだと学びました。
Cさん
以前急変に立ち会った際、先輩看護師が速やかに処置や物品準備にあたっていたのを覚えています。研修ではその時の状況を振り返りながら、すべき対応について考えることができました。また、起こりうる状況を想定しながら処置を練習したり、物品の使い方も学ぶことができました。今後は状況に合わせて自分にできることは何かを考えながら、行動していきたいと思います。
患者さんの生命が関わる場面で、患者さんの状態から必要な処置や対応を冷静に判断し、迅速に行動するためには、看護師として果たすべき役割を理解し、必要な知識や対応を常日頃から学習しておくことが重要なのだと改めて感じました。先輩看護師から学ばせて貰う事も多いですが、後輩が一生懸命仕事をしている姿や、患者さんのために熱心に学習に励む姿を見ていると、私も頑張ろうといつも刺激をもらっています。患者さんの急変時には一刻も早い救命処置が求められるます。どんな時でも患者さんに安心・安楽な看護や医療を提供できるよう、これからも病棟全体で力を合わせて頑張っていきます。
2022/12/28
今日は7D病棟のNです。
新人看護師さんを紹介します。
当院への入職者は、北海道から沖縄まで各地から集まっています。
当部署の新人看護師は、神奈川県、新潟県、広島県から就職しました。
入職して半年以上経過し、できることも増えると、少し緊張もほぐれ、皆生き生きと働いています。
また、今でも初めて行う処置は先輩にみてもらってから実際に患者さんに行います。
写真は、実際に採血の練習を先輩に教えてもらっているところです。
このように、患者さんに安心して、かつ安全に処置が実施できるように訓練してから実践しています。
これからもできることを増やせるよう、訓練を続けていきます。
2022/12/26
5A 病棟 Kです。
先日行われた第2ブロック支部総合訓練の様子をお伝えします。
日本赤十字社は全国を7つのブロックに分けてブロック単位ごとに救護体制を敷いています。
神奈川県は関東1都6県と山梨県、新潟県を1つの区域とした第2ブロックに所属しています。神奈川県では対応できない大規模災害が発生した場合に、県境を跨いだ協力体制が必要になるため、このような訓練が毎年開催されています。
今年度は神奈川県が担当となり、秦野市、神奈川県庁、平塚保健所、多数のボランティアさんなどにもご参加いただき市内の小学校に想定された避難所を巡回し、問題点の抽出とその対応について考え、調整を図る訓練となりました。
当院からは、救護班1班、その構成は、医師1名、看護師長(係長)1名、看護師2名、主事2名と訓練支援者として医師2名、看護師長2名、コメディカル4名の職員が派遣されました。
訓練は2日間にわたり開催されました。1日目は、チームビルディングに始まり、2か所の避難所を回りながら避難所アセスメントの実際の訓練です。
1か所目の小学校では他施設の救護班と協働し、感染対策をしながら、避難所の責任者などに情報収集し、避難者の情報収集を行っていきました。しかし、初めて使用する災害診療記録やJSPEEDの記録に翻弄され、総合的なアセスメントまでには至らず、反省点も多く抽出され、移動の中でその点について振り返り、2回目の避難所へ向かうこととなりました。
2か所目は、多職種で意見交換を行ったことで、2人1組となり、ローラー作戦ですべての傷病者に対応し、急変された避難者の対応、その後の搬送にまでつなげることが出来ました。また車で避難している方の情報収集とその方の体調にまで気づかい、避難所のハード面まで総合的にアセスメントすることが出来たようでした。
実動訓練の翌日は、グループワークでどのような点に配慮し、2回目をどのように動いたか、振り返りしながら、さらに自分たちの役割を考える機会となり、今後の実動に向けた課題も見出すことが出来たとおもいます。
このような訓練を繰り返し、有事に備え、準備をすすめていきたいと思います。また、有事の際はより連携強化が求められるため、平時から、赤十字施設間での顔の見える関係づくりを積極的に進めていきたいと思います。