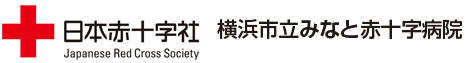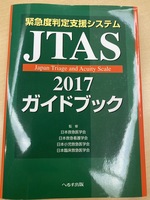2020/8/12
~こんにちは、5C病棟Iです!助産師、看護師、医師、看護助手、クラークを合わせると約40人のスタッフが働いています。
産婦人科は病棟外来一元化のため、病棟も外来も同じスタッフが行き来して患者と関わっています。継続看護を行いやすく、定期的に外来受診や治療入院される患者とは自然と距離感が近くなり、信頼関係も築きやすいと感じています。
産科は新生児の誕生に関わることはもちろん、妊娠初期から産後1か月まで通して母子ケアを行っています。複雑な事情を抱えている方の出産を支える機会も多く、安心して育児がスタートできるように妊娠中から他職種や地域の保健師などと連携しています。退院後の生活をイメージして具体的な準備が整えられるような支援を心がけています。
婦人科は女性特有の疾患や、癌患者の看取りまで、女性の人生のあらゆるステージに関わっています。高齢の方も多く、患者・家族の思いを尊重した意思決定支援や、最小限の不安で治療に向き合えるような関わりを大切にしています。
1分1秒を争う場面もあるため、スタッフ同士で頻繁に声をかけ合って患者さんの安全を守っています。スタッフの連帯感がとても強く、やりがいの大きい産婦人科病棟でぜひ一緒に働きませんか?
2020/8/11
こんにちは☆ 救急病棟Mです!
今回は院外勉強会についてお伝えしたいと思います。救急病棟・救急外来で働く上で院外勉強会に参加し学びを深めること、資格取得に努めたりすることは個々の看護スキルを上げるために必要なことです。
私は「JTAS」という資格取得の勉強会に行ってきました。「JTAS」は救急外来において、患者さんのトリアージを適切かつ迅速に行うことができるようになるためのものです。勉強会に参加することで、知識の充実や多角的に患者さんを看る視点を学ぶことができました。勉強会後からは救急外来において患者さんのトリアージを行う場面で実践に活かす事ができています。
今回私が受講したのは、「JTAS」でしたが、その他にも「ICLS」「JPTEC」「JNTEC」など多くの勉強会があります。部署では、「院外勉強会」への参加は積極的にさせてもらえるため自分自身のスキルアップもでき、やりがいにも繋がますよ~!
2020/8/5
こんにちは、外来係長の丸です。
今回は、地域と病棟をつなぎ、患者さんの療養生活を支える力持ち(?!)のナースがたくさん働いている外来から紹介をします。
当院はがん診療やアレルギー診療の拠点病院として横浜市から委託され、数々の政策医療を行っています。中でもアレルギーセンター所属の上原直子さんは、アレルギーエデュケーターとして医師と共に横浜市、神奈川県で精力的に活動し、外来でも1,2を競うキラリナースです!
それでは早速インタビューをしてみましょう♡
Q「アレルギーエデュケーターになろうとしたきっかけを教えてください」
A「小児アレルギーエデュケーター(以下PAE)は2009年度より小児臨床アレルギー学会が認定した資格です。私は3期生としてとして試験に合格しました。アレルギーを診療する小児科医師よりPAEを目指してみないか?とお話しをいただきました。アレルギーセンターで勤務を始めて3年目となり、患者指導する力をつけたいと思いPAEを目指しました。」
Q「看護師としてアレルギーエデュケーターのやりがいはどのようなことでしょうか」
A「日本人の2人に1人は何らかのアレルギーを持っていると言われています。 アレルギー疾患がある事で日常生活を不安な気持ちで送る患児と保護者がいます。 PAEの研修で学んだカウンセリング技法を使いながら患児、保護者へ指導することで対面した直後と帰る時では表情が柔らかくなり前向きな気持ちで生活できるようになった時PAEとしてやりがいを感じます。」
Q「今、学校で学んでいる看護師の卵さんにメッセージをお願いします」
A「今、座学や実習で学んだ事は必ず臨床で活かされます。ぜひ、みなと赤十字で一緒に看護を共有出来ることを楽しみにしてます。」
2020/8/4
7A病棟の係長佐伯です。
7A病棟のスタッフは自主性があって、働きやすい職場を作るために取り組んでいます!
その一貫で、6月25日に病棟で褥瘡の勉強会を行いましたのでご紹介します。
COVID19感染予防対策はすっかり身について、換気をしっかり行いながら、短時間で集まりました。 スキンケアは基本的なことだからこそ、繰り返し、初心に戻っておさらいすることが大事! 新人も、ベテランも、管理者もみんなでお勉強です。
スキンケア委員さんが「褥瘡とは?」「基本的なケア」「病棟のあるある」「電子カルテですぐ見られる資料」「記録のしかた」などを丁寧にリマインドさせてくれました。 日常行っていることだけれども、あらためて学ぶ機会があることで、曖昧なところを確認できたり、意識を高められるんだなあ・・・ 2年目のスタッフも係活動として勉強会の企画に関わりました!頑張ったね!
安心な職場、働きやすい職場を自分たちで作っていくということは、こういう活動の積み重ねなんだなあと思います。高齢の患者さんのデリケートな皮膚を守るために、しっかりスキンケアに取り組んでいこう!と気持ちを新たにできました。
次回は来月、化学療法の勉強会をする予定!今、熱心に勉強している3年目が企画してくれます! がんばれ~~!
2020/8/3
5A病棟 係長 田鎖です 今回は、精神科病棟内の隔離室を紹介します。 (当院のスタッフでも、室内を見たことはない人がほとんどです)
患者さんの中には、他の方と接することが刺激となり病状を悪化させてしまう方や、自身では衝動を抑えきれずに他者や自身、物などを傷つけてしまう方などがいらっしゃいます。そのような方々を精神保健福祉法に則り「隔離」し刺激から守る事も、精神科の治療においては必要となる場合があります。
精神科病棟の隔離室(保護室)というと、「壁はモスグリーンなどの単色に塗られ、窓は磨りガラスで鉄格子がついている」というイメージを抱く方も少なくないと思います。しかし、当院の隔離室(保護室)は、写真の通り木目調を基本としており、また窓からはベイブリッジが見えるなど、リラックスして過ごせるような環境になっています。
ハード面ではこのような環境を提供していますが、自分の意志では出ることが出来ない空間で過ごさなくてはならない状況は、強いストレスがかかります。そのストレスを少しでも軽減できるよう、看護師の倫理綱領を見失うこと無く、相手の立場になってその感情を捉え、少しでも安楽な時間を提供するため、日々悩みながら看護を提供しています。