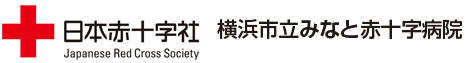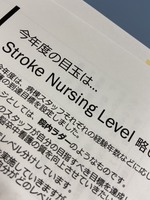2020/10/7
こんにちは!5D病棟のAです。
今日は勉強会の様子について紹介していきたいと思います。
様々な疾患を抱えた患者さんが入院するため、自部署の勉強会はもちろん、産科・整形外科・内分泌などの他部署の勉強会へも積極的に参加させてもらっています。
また、5D病棟のスタッフは救急外来に搬送されてきた小児の患者さんの対応をすることもしばしば…。過去にあった事例に基づいてシミュレーションを行うことで、急変時に適切に対応できるように訓練しています。
最近では自部署で、小児科医師主催の熱性けいれんの勉強会を行いました!
病態生理とけいれん発作時の初期対応、そして医師はどういう考えで処置を行い、看護師にはどうしてほしいかを確認しました。医師と看護師間で共通の考え方を持っていることもスムーズに動けるようにするためにはとても大切ですね…!
今後みんなで学びを深めていきます!
2020/10/2
6B病棟は、呼吸器内科、外科、耳鼻咽頭科、アレルギー科を主に担当している病棟です。
先日呼吸器外科の医師から勉強会を行ってもらいました!その様子をお届けしたいと思います。
写真は、気胸や肺癌の手術について、どのように行われているのかを動画や写真で教えてもらっている様子です。
勉強会に参加した、新卒看護師Sさんに感想を聞きました!
Sさん:「自己学習だけでは、あまりイメージができなかったため映像や写真をみることでイメージしやすくなりました。自己学習より勉強になりました。」
たしかに病棟看護師は、普段手術室に入ることがないため、どのように手術が行われているかについて学ぶ良い機会となりました。手術のリスクを知ることにより術後の異常の早期発見や退院指導に活かしていきたいと思います。
6B病棟は勉強会も多く、勉強会に参加することは自分のスキルアップにつながるため、より良い看護を提供できるよう積極的に取り組んでいます。
2020/9/29
こんにちは。脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の河野です。
先日の活動紹介に引き続き、今回は、今年度の活動の目玉である、「SNL」を紹介したいと思います。これは「Stroke Nursing Level(ストロークナーシングレベル)」という私が考えた造語の頭文字です。病棟には、看護師としての経験年数はもちろん、脳卒中看護の経験年数も様々なスタッフがいます。すべてのスタッフに同じような教育をしても、あるスタッフには難しかったり、またあるスタッフには物足りなかったりと、効果的な教育にはなりません。
そこで私は、脳卒中看護の実践能力に対する目標設定を4段階に分けました。レベルⅠは「勉強会に参加し知識を得る」、レベルⅡは「知識を活用し看護展開を実践する」、レベルⅢは「他者を巻き込んで看護展開を実践する」、レベルⅣは「指導的な役割がとれる」というようなものです。
スタッフにはそれぞれ自分がどのレベルの目標を目指すのか考えてもらい、目標達成に向けて1年間勉強会の参加や日々の看護実践に取り組んでほしいと説明しました。
この教育計画が、ストロークナーシングレベル「SNL」です。
このシステムにより、スタッフが主観だけではなく客観的な相互評価で自分の成長を可視化し実感することができます。初心者はもちろん、脳卒中に興味があれば段階的に学び、成長していくことができます。
と言っても、まだ始めたばかりで粗削りな取り組みです。師長さんの指導を受けながら、より洗練された教育計画に仕上げていくことが私の課題です。私自身、認定看護師として看護実践能力とともにスタッフの教育・育成能力を磨きながら、スタッフと共に脳卒中看護の奥深さ、おもしろさを追求していきたいと思います。
2020/9/28
こんにちは。脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の河野です。
脳卒中は日本の死亡率第3位の疾患で、命が助かったとしても重篤な後遺症が残ることも少なくありません。重篤化を食い止め、機能回復のために早期からリハビリを開始し、生活の再構築を余儀なくされた患者さんに寄り添いながら支援をしていく、という役割が脳卒中患者に関わる看護師には求められます。私は、患者さんがその人らしい生活を再開できるように手助けができる、ストロークナースを育成したいと考えています。
私の認定看護師としての主な活動の1つ目は、所属部署のスタッフに向けて脳卒中に関する勉強会を開催することです。昨年度から脳卒中看護の質の向上のため、「脳卒中勉強会シリーズ」と題して定期的に勉強会を開催しています。活動の2つ目は、日々の看護実践の中でスタッフから相談を受けたり、気付いた点についてアドバイスをしたりすることです。私自身、看護の方向性について迷うことも多く、スタッフと共に患者さんにとって最善の支援を模索する毎日です。
次回は今年度の活動の目玉を紹介します。
2020/9/27
がん性疼痛看護認定看護師のNです。私は緩和ケア病棟に勤務しています。
皆さん、緩和ケアというと、どのようなことを想像するでしょうか?
「ホスピス」「がんの終末期」「退院しない」「暗い」「穏やか」「ゆったり」などなど、様々な印象があるかと思います。
緩和ケアとは、がんと診断を受けた時から提供されるケアです。そのため、積極的な治療を受けながら平行し、苦痛の軽減、緩和ケアを受けるというのが今の医療の在り方です。
一般病院に入院中や通院中の方にも緩和ケアは提供されます。治療中の患者さんには緩和ケアチームが介入し、痛みや辛い症状のマネジメントを行っています。
そして緩和ケア病棟は、積極的な治療はせず、痛みやその他の苦痛症状が和らいで、より豊かな人生を送ることができるように支えていく病棟になります。そのため、その人らしい生活が送れるような在宅調整も積極的に行い、患者さんの望みを支える看護を大切にしています。
私は、認定看護師/看護実践者の一人としてスタッフや患者さんと共に悩んだり、喜びを分かち合ったりしながら、患者さんの苦痛が緩和でき、患者さんの真の望みを探り、それぞれの望みに合った選択ができるような看護を大切にしています。
看護師は患者さんやご家族のために何かできることをしたいと願っています。しかし、実際は患者さんやご家族から与えてもらう力はとても大きいと感じています。だからこそ、忙しく大変なことがあっても頑張っていけるのではないでしょうか。
そんな看護の楽しさを一人でも多くの方に実感してもらえるよう認定看護師としても頑張っていきたいと思います。