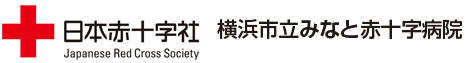2020/12/28
こんにちは。緩和ケア病棟のSです。
緩和ケア病棟と病棟薬剤師との連携について紹介したいと思います。
緩和ケア病棟では、患者さんへの苦痛の軽減の一つの手段として、麻薬の使用があります。その麻薬を適切に管理するため、毎日リーダー看護師と病棟薬剤師は麻薬の受け渡し、残数の確認など連携を取り、共に実施しています。
また、患者さんがご自宅などへ退院される際には、本人・ご家族へ服薬指導を実施してもらい、自宅でも、不安なく過ごすことができるよう関わってもらっています。特に、自宅に帰られる際には、疼痛増強時などの痛み止めの使用方法が重要になってくるため、患者さんが一人になる時間やどのように家族を巻き込んで指導できるかを確認しながら、指導を実施しているそうです。
患者さんへの安全な緩和ケアを実施するため、多職種で協働しています。
2020/12/23
外来師長の小森です。赤十字看護師同方会の役員をしています。
今回は、当院の敷地の看護師の顕彰碑についてご紹介します。
この顕彰碑は、戦争に、災害に、また病床に傷つき病める方々に愛の手をさしのべ、看護に尽くされた赤十字救護員の献身的な活躍をたたえ永遠の世界平和を願い建立したものです。毎年、日本赤十字社看護師同方会によって献花を行っています。
日本赤十字社看護師同方会とは、100年以上の歴史を持ち、会員相互の親睦を計り、後輩看護師の育成や赤十字事業推進のための協力体制の強化を図る活動をしている組織です。
会員は、赤十字施設に勤務する看護職員や赤十字看護教育施設で学んだ人(正会員)と事業に協賛してくださる看護職でない人(賛助会員)で構成されています。全国会員数は25000人以上、神奈川県支部では330人加入しています。
今年は、みなと赤十字病院の師長会の師長さんたちで献花をしました。
赤十字看護師として、先輩方の思いを引き継ぎ、患者さんへ愛の手をさしのべる看護をしていきたいと振り返る日となりました。
2020/12/17
こんにちは、5C病棟のMです。
今回は私の休日の過ごし方を紹介します!
社会人になってから趣味としてボルダリングを始め、そろそろ2年になります。
ボルダリングは「ホールド」という突起物を掴んで壁を登っていくスポーツで、東京オリンピックの新種目として追加されたことで少し話題になりましたよね。
現在は、新型コロナ感染症の感染状況を考慮しながら、体温計測やマスク着用、人数制限(密にならないように)といった対策のもと注意しておこなっています。
ボルダリングを始めてから休日の楽しみが増え仕事と休日のメリハリがつくようになったことや、筋力や体力がつき体調を崩しにくくなったことなど、公私ともに良い影響があるように感じています。
みなさんも、みなと赤十字病院で公私共に充実した看護師ライフを送りませんか?
2020/12/11
①つづき
例えば…
1. 両足をそろえ、背筋を伸ばして立つ
2. 「1」と数えながら右足を右横に大きく開く
3. 「2」と数えながら、1の状態にもどる
4. 「3」の代わりに手を叩き、左足を左横に大きく開く うまくできなくても、間違えて笑って、試行錯誤しながら楽しんでみてください(^^) 「笑うこと」も、心や体にとって良い影響を与えることは、表情筋や腹筋などの筋肉を刺激し、免疫効果も高めてくれ、認知症予防にも効果的です。
日本は超高齢化社会にあり、病院だけでなく、社会全体で介護を要する高齢者も増えています。 私の両親もいつまでも元気でいて欲しいし、自分も元気でかわいいおばあちゃんになりたい。 困っていそうな高齢者に会ったら迷わず声をかけられるようになりたい。 いつか訪れるそのときに備え、理解を深める機会となった健康生活支援講習でした。
2020/12/8
先日行いました「健康生活支援講習短期講習」について、当院のインストラクター2人から記事が届きました。
健康生活支援講習は、日本赤十字社が開催する講習会の一つです。本講習は、高齢期を健やかに生きるために必要な健康増進の知識、高齢期への理解を深め、高齢者の支援や地域活動に活かすことを目的とした講習会です。
こんにちは、総務課広報担当の鈴木 & 救急災害業務課の蛭川です。 今回は院内の看護師・看護助手対象に開催した、健康生活支援講習の様子をお届けします。
今回のテーマは「認知症」。 生活習慣の重要性にはじまり、加齢に伴う体と心の変化、認知症の予防方法や症状・対応についての講義、バランス運動やコグニサイズを行いました。 さて、みなさん、「コグニサイズ」をご存じでしょうか? コグニサイズとは、英語のcognition (認知) とexercise (運動) を組み合わせてcognicise(コグニサイズ)と言い、運動と脳の活性化を一緒に行うことで認知機能の維持や改善を目指すものです。 ②につづく