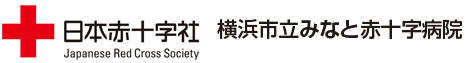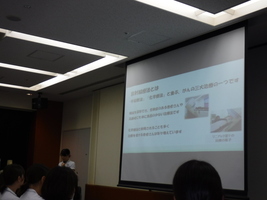2018/11/13
こんにちは。7Aブログ担当のNです。
今回はラダーレベルⅡの第4回実地指導者研修についてお伝えします。
みなと赤十字病院では、院内研修環境が整っており、
自分のレベルに合わせた研修を受講することができます。
実地指導者研修では、講義とグループワークを行い、
新人への指導方法や困っていることの共有を行っています。
研修というと堅苦しいイメージがありますが、和気あいあいとした雰囲気でやってます。
日々、悩みながら新人指導を行ってますが、プリセプター同士で悩みを共有することで、
悩んでいるのは自分だけじゃないんだと安心できます。
また、1年間を通して同じメンバーとグループワークを行うので、
他部署同士で横の繋がりを作ることもできます。
新人と共に成長していきたいと思います。
2018/11/6
こんにちは。
看護部ブログ担当のSです。
実践者ラダーⅣの研修会後にスペシャリスト報告会が行われました。
今回の報告会はスペシャリストとスタッフがコラボした実践を発表しました。
1題目は手術室看護師と小児救急看護認定看護師がコラボしたプレパーレーションの事例
2題目は神経内科病棟看護師とリエゾン、脳卒中リハビリテーション看護認定看護師による
せん妄患者がケアによって変化した事例でした。
当日は100名以上の参加があり、認定看護師と病棟スタッフがどのように看護したのか、
認定看護師の専門的なアセスメントが実践した看護の意味と結びつき、
充実した報告会となりました。
発表者と一緒に看護していたスタッフたちもきっと達成感が得られたと思います。
2018/10/1
こんにちは!
6B病棟ブログ委員のMです。
今回は腹部のフィジカルアセスメントの研修についてお伝えしたいと思います☆
最初に講師である先輩看護師から腹部の臓器についての講義があります。
学生時代から勉強していますが、実際の経験談も交えながら教えてくれるため、
「なるほど!」と思うことがたくさんあります!
その後、腹部の観察方法について勉強し、お互いに患者役になり、聴診・打診を行います。
実際にやってみると、わたしたちのお腹にも意外とガスや便がたまっていることがわかります...。
その後は「嘔気・嘔吐がある患者さんが病院を受診してきた」という事例をチームで考えます。
嘔吐の原因をふまえたうえで、根拠のある観察点を話し合いながら上げていきます!
1チームに1人いるアドバイザーから助言をいただきながら、活気のあるディスカッションをすることができました!
研修で学んだことは、病棟にいる患者さんの観察にも活かされています。
まだまだ学ぶことは多いですが、先輩方にアドバイスをもらいながら日々精進していきたいと思います!
2018/9/27
6Aブログ担当Tです。
院内ラダー研修でコミュニケーションについて学びました。
学生の頃にコミュニケーションの講義を受けて以来、久しぶりの講義でしたが、
改めて「アサーティブ」について日々の患者さんとの関わりを振り返りながら考えることができました。
「DESC法」を活用し、否定的、肯定的な患者さんの訴えに対する自分の心境の変化も感じることができました。
受講した看護師は2~3年目のスタッフで、日々の患者さんとの関わりの中で悩むことが多く、
どうしたらいいのかと苦闘していた時期でもあったため、明日からの患者さんとの関わり方の道しるべになりました。
2018/8/20
こんにちは
7C病棟、看護師3年目のAです。
赤十字病院の看護師には、救護員としての役割があります。先日、災害救護研修Ⅰを受講したので、
感想をお話したいと思います。
得に印象に残っているのが『慢性疾患患者の災害対策』の重要性です。
7C病棟は循環器内科・心臓血管外科病棟で、心不全の患者さんが多いです。
慢性心不全は日常生活における自己管理が重要で、怠薬や飲水過多・脱水、食生活の変化、血圧変動などですぐに増悪してしまいます。災害時には薬や飲水量の確保が難しく、また身体的・精神的ストレスから血圧上昇や心負荷に繋がり、容易に心不全が増悪することが考えられます。
こうしたことが予測される中、普段から薬や水分を余分に確保しておくこと、酸素療法を行っている人は移動用の酸素の準備や業者の連絡先を把握しておくこと、その他必要物品の準備や介護者の確保など、事前に対策をとっておけることはたくさんあります。そのことを常時から、生活指導と併せて患者さんに伝え、災害への備えの啓発をすることも私たち看護師の役割と言えます。
『災害救護』と聞くと、被災地に派遣され現地で活動する看護師を想像し、自分には遠い世界のように感じます。しかし、日々の看護で、患者さん自身が自分を守るために出来ることもたくさんありますね。