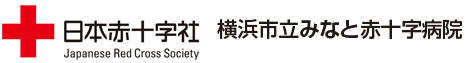2021/1/14
7D病棟の栄養士との連携


こんにちは!7D病棟の看護師Aです!
7D病棟は血液内科・内分泌内科・リウマチ科の混合病棟です。
化学療法中、治療後に食事がとれない患者や糖尿病で食事療法が必要な患者が多くおり、栄養士と連携をとりながら日々看護を行っています。今回は7D病棟担当の管理栄養士のTさんにインタビューさせて頂きました~!
Q1:管理栄養士の病棟での役割を教えてください。
→A1:病棟では食欲不振の方、食事形態の調整が必要な方の食事調整を行っています。
食事の時間に訪室し、入院中の食事状況の確認、普段の食生活、嗜好などを伺っています。それらを踏まえ、少し
でも喫食量が上がるような食事提案をさせて頂いています。
Q2:看護師や医師とどのように連携をとっていますか?また、7Dスタッフのイメージも教えていただきたいです。
→A2:食事状況より喫食量の低い方に聞き取りを行うこともありますが、主に医師や看護師から依頼があった際に訪室 することが多いです。
依頼後すぐに訪室することは業務上難しいこともありますが、次の食事までには調整できるよう心掛けています。
7Dの皆さんは温厚なイメージがあります^^
Q3:化学療法後の食欲不振や味覚障害がある患者に提案する食事にはどんなものがありますか?
→A3:みなと食という食事があります。みなと食とは(麺類や果物、アイス等)のど越しの良い物を少量楽しめる食事になっています。
みなと食の対象外となる方には、提供中の食事をベースに主食変更、形態調整、補食の追加などを提案させて頂いています。
Q4:糖尿病患者の栄養指導で配慮していることはありますか?
→A4:個々の生活背景を考慮し、退院後も治療を継続できるような指導を心がけています。
栄養士が患者の元で親身に聞き取りを行い、専門的な知識をもとに個別性に合せた食事を提案して頂けることで、患者の食事量が増えることにつながっています!また、食事が入院中の楽しみの1つになっていると感じています。看護師からも患者の疾患や治療の状況などの情報共有を行い、より良い食事を提供できるようにしています。Tさんインタビューにご協力ありがとうございました!!
※写真は当院の「みなと食」です。みなと食は、化学療法・放射線治療中で副作用による食欲不振がある方、かつ治療上食事制限がなく一般職を召し上がれる方を対象の食事です。