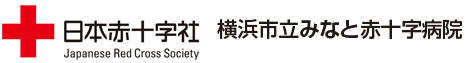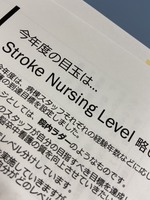2020/10/7
こんにちは!5D病棟のAです。
今日は勉強会の様子について紹介していきたいと思います。
様々な疾患を抱えた患者さんが入院するため、自部署の勉強会はもちろん、産科・整形外科・内分泌などの他部署の勉強会へも積極的に参加させてもらっています。
また、5D病棟のスタッフは救急外来に搬送されてきた小児の患者さんの対応をすることもしばしば…。過去にあった事例に基づいてシミュレーションを行うことで、急変時に適切に対応できるように訓練しています。
最近では自部署で、小児科医師主催の熱性けいれんの勉強会を行いました!
病態生理とけいれん発作時の初期対応、そして医師はどういう考えで処置を行い、看護師にはどうしてほしいかを確認しました。医師と看護師間で共通の考え方を持っていることもスムーズに動けるようにするためにはとても大切ですね…!
今後みんなで学びを深めていきます!
2020/10/6
~こんにちは!救急病棟Sです!
今回は少し夏休みをいただいた時の事を書きたいと思います☆
いただいたお休みで母の誕生日祝いも兼ねて、長野県の蓼科に旅行をしてきました!
コロナの影響もあって、電車ではなく車でお出かけです。
実家の方は一家に1台の車!ではなく…1人1台の車を持つ群馬県なので、少し長距離なドライブ気分で行ってきました☆
もちろん家族みんなマスクを着用しています!笑
蓼科の自然に囲まれた素敵な旅館に泊まって温泉を楽しんで、次の日はビーナスラインをドライブして、マイナスイオンと澄んだ空気に癒されて帰ってきました。
このコロナの中で自粛ばかりですが、ちょっとした気分転換も大切だなと思いました!
アルコール消毒のし過ぎでちょっと手荒れ気味ですが、これも自分や周囲の人を守るために重要な事なのでハンドクリームを味方にしながら頑張っていきたいと思います!
2020/10/2
6B病棟は、呼吸器内科、外科、耳鼻咽頭科、アレルギー科を主に担当している病棟です。
先日呼吸器外科の医師から勉強会を行ってもらいました!その様子をお届けしたいと思います。
写真は、気胸や肺癌の手術について、どのように行われているのかを動画や写真で教えてもらっている様子です。
勉強会に参加した、新卒看護師Sさんに感想を聞きました!
Sさん:「自己学習だけでは、あまりイメージができなかったため映像や写真をみることでイメージしやすくなりました。自己学習より勉強になりました。」
たしかに病棟看護師は、普段手術室に入ることがないため、どのように手術が行われているかについて学ぶ良い機会となりました。手術のリスクを知ることにより術後の異常の早期発見や退院指導に活かしていきたいと思います。
6B病棟は勉強会も多く、勉強会に参加することは自分のスキルアップにつながるため、より良い看護を提供できるよう積極的に取り組んでいます。
2020/10/1
緩和ケア病棟のSです。 このたび、緩和ケアセンターのホームページに緩和ケア病棟の紹介動画がアップされました。 緩和ケア病棟の病室やデイルーム、眺めの良いデッキなども紹介されているので、下記をクリックして是非ご覧下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=ccSwOst__1E
2020/9/29
こんにちは。脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の河野です。
先日の活動紹介に引き続き、今回は、今年度の活動の目玉である、「SNL」を紹介したいと思います。これは「Stroke Nursing Level(ストロークナーシングレベル)」という私が考えた造語の頭文字です。病棟には、看護師としての経験年数はもちろん、脳卒中看護の経験年数も様々なスタッフがいます。すべてのスタッフに同じような教育をしても、あるスタッフには難しかったり、またあるスタッフには物足りなかったりと、効果的な教育にはなりません。
そこで私は、脳卒中看護の実践能力に対する目標設定を4段階に分けました。レベルⅠは「勉強会に参加し知識を得る」、レベルⅡは「知識を活用し看護展開を実践する」、レベルⅢは「他者を巻き込んで看護展開を実践する」、レベルⅣは「指導的な役割がとれる」というようなものです。
スタッフにはそれぞれ自分がどのレベルの目標を目指すのか考えてもらい、目標達成に向けて1年間勉強会の参加や日々の看護実践に取り組んでほしいと説明しました。
この教育計画が、ストロークナーシングレベル「SNL」です。
このシステムにより、スタッフが主観だけではなく客観的な相互評価で自分の成長を可視化し実感することができます。初心者はもちろん、脳卒中に興味があれば段階的に学び、成長していくことができます。
と言っても、まだ始めたばかりで粗削りな取り組みです。師長さんの指導を受けながら、より洗練された教育計画に仕上げていくことが私の課題です。私自身、認定看護師として看護実践能力とともにスタッフの教育・育成能力を磨きながら、スタッフと共に脳卒中看護の奥深さ、おもしろさを追求していきたいと思います。