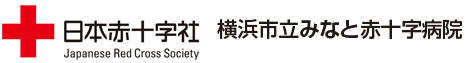2022/9/2
こんにちは 6C病棟のIです。
今回は今年6C病棟に配属された新卒看護師3人からお話を伺いました。
入職して4か月がたち、3人とも「ようやく慣れてきた」や「チームメンバーの1人として働けるように頑張りたい」「ラダーを無事取得できるようにしたい」「同期と協力しながら頑張っています」といった声が多く聞かれました。
この時期の新卒看護師さんは少しずつ日々受け持つ患者さんの人数が増え日勤帯では約4~5人、夜勤帯では6~7人ほどとなっています。
また受け持つ疾患としては、泌尿器科の短時間の手術や乳がん摘出手術・皮膚疾患といったもので、1日の勤務時間中にある入院・手術などを先輩からアドバイスをもらいながら1人で責任をもって受け持つための練習をしています。
どの新卒看護師さんも教えてもらったことをすぐ吸収してくれているので、すでに頼もしい存在になっていて今後の成長がとっても楽しみです♪
これからも病棟全体で新卒看護師さんがのびのびと成長できるような環境を作っていきたいと思います!
2022/9/1
7B病棟のWです。
今回は慢性疾患パンフレットについて紹介します。慢性疾患とは、様々な原因で発症し、再発・合併症の発症予防や身体機能の維持・改善を目指しながら、長期にわたる治療や管理が必要となる疾病のことを指します。
7B病棟には内科的治療を受けている方が多く、退院後も疾患と付き合いながら、日常生活の中で治療を続けていく必要がある方が多くいらっしゃいます。そのため、患者さんやご家族が少しでも安心して地域に戻れるよう「慢性疾患パンフレット」を用いた指導行うことで、退院に向けた準備をサポートしています。
7B病棟では、主に胃・膵臓・腸・胆嚢などの消化器疾患(癌を除く)を持つ患者さんを対象に退院指導を行っています。指導では患者さんやご家族に、慢性疾患パンフレットを用いて食事や活動面などの生活における注意点について説明を行い、お話を聞かせて頂きながら、退院後の生活における課題を明確にします。そして、必要に応じて院内の栄養士や薬剤師と連携したり、ケアマネジャー・訪問看護師などの地域ケアスタッフとも連携します。また、日常生活の中でも患者さんが継続して治療が行えるよう、方法や手段についても一緒に考え、今後の生活をイメージしながら、退院に向けた準備が出来るよう支援しています。具体的には、退院後も患者さんが内服管理が出来る様に薬剤を一包化したり、日々の食事で気をつける点の指導、肝機能障害がある方など特に排便コントロールが重要となる方の場合には具体的な排便頻度の目標を設定したりします。
院内で患者さんと関わっていると、ついその方の"患者さん"としての姿ばかりが目に映ってしまいますが、その方の本来の"生活者"としての姿にもきちんと目を向け、今後を見据えた看護をしていきたいなといつも思います。入院期間という限られた時間の中ではありますが、医療チームで連携し、患者さんが疾患と付き合いながら、その方らしく生活を築いていけるようこれからも支援していきます。
2022/8/31
こんにちは。
看護部の曽我です。
10月8日(土)に文化放送ナースナビで
オンライン病院合同説明会が開催されます。
当院がその説明会に参加することとなりました。
当院の概要及び教育体制など説明いたしますので
多くのかたの参加をお待ちしております。
詳しくは添付したファイルをご覧ください。
2022/8/30
外来Kです。
今年は4月から外来に2名の育休明けスタッフが仲間入りしました。
どちらも病棟経験のある頼もしい方々です。
Mさん「ずっと同じ科で勤務してきたため、異動して初めて経験することも多く、加えて近々救急外来勤務にも入るため、とても緊張していますが頑張ります。」
Oさん「病棟と外来とでは勝手が違う部分もあり、戸惑うことも多々ありますが、病棟経験で培った知識などを外来看護における指導の場面などで活かすことができています。頑張ります。」
お二人ともまだ緊張しながら勤務をしているようですが、元気に答えてくれました。
外来では、通勤時間を利用して仕事と家庭の切り替えをするなど、ワークライフバランスを意識しながら日々勤務しています。外来スタッフはママさんNsも多く、仕事のことのみならず、子育ての相談もできる環境なので、外来一同支え合っています。
写真はある日のママさんNsの皆さんです。
2022/8/29
みなさんこんにちは!検査課のAです。
当部署の内視鏡では「消化器内視鏡技師」の資格を持っているNSが
複数名勤務しています。
消化器内視鏡技師のSさんにこの資格についてインタビューをしました。
Sさんは、検査課に配属された時、内視鏡は全く未知の領域で
わからないことも多くあり、1年が経過した頃にこの資格を知ったそうです。
「消化器内視鏡技師」はNSも取得できる資格であり、機器の消毒等専門知識、
処置具の取り扱いについての知識を持ちながら、医師の検査介助を安全にかつ円滑
に行うことができるようになるそうです。
勉強したことが、普段の検査介助に結びついたり、患者さんへの適切な声かけにつながっていると感じた時に、資格をとって良かったと実感するそうです。
Sさんのお話を聞いて、
現場で、学んだことを活かし、患者さんにも還元できる実践に役立つ素敵な資格だな
と思いました。受験資格には、勤務経験と年数を重ねる必要があります。
長い道のりですが、私も、まず試験を受ける資格を得るために経験と知識を重ねていこうと思います。