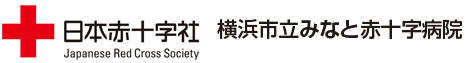2022/1/12
6A病棟(脳外科・神経内科・眼科)のSです。
今日は、4月に入職し約半年が過ぎた新卒看護師さんにインタビューしたので紹介したいと思います。
Tさん:受け持つ患者さんの人数が増えて大変なことも多いですが、ペアやフォローの先輩に助けてもらって少しずつできることが増えてきました。脳卒中の後遺症で言葉が上手くはなせない方との日々の関わりで、コミュニケーション方法を工夫して患者さんが言いたいことを受け取れた時はうれしくなります。そのような関わりがもっとできるように成長したいです。
Oさん:毎日大変ですが、患者さんから感謝されると自分の行った看護が患者さんにとってよかったのかなと思えます。看護師を目指して勉強して実際に看護師になることができて、やっぱり看護師っていいなって思える瞬間があるのでこれからも頑張りたいです。
お二人とも、とてもキラキラしていて素敵でした!
これからも新卒看護師さんがゆっくりと成長できるよう病棟全体で応援したいと思います!
♯新卒看護師
♯脳卒中
♯コミュニケーション
♯感謝
♯看護師っていいな
2022/1/11
救急病棟に所属している大松 真愛と申します。
横浜市立みなと赤十字病院 救急病棟のご紹介です。
私の所属している救急病棟という部署は、救急病棟と救急外来の両方を兼務している部署です。救急病棟では、緊急入院となった患者さんへの全身管理や看護ケアから退院支援まで、様々な病期にある患者さんへのケアや支援を行います。救急外来では、突然の怪我や病の発症で救急搬送されてきた患者さんの初期対応を行います。
新卒看護師も所属しており、院内異動者や既卒入職の方も多くいらっしゃいます。私自身も卒後3年目のときに既卒入職しました。救急という部署柄、覚えることや自己学習していくことは非常に多く苦労しましたが、相談しやすい上司、病棟の働きやすい雰囲気、しっかりした教育体制が整っており、働きやすさを感じています。もっとこの部署や病院に貢献していきたいと思うようになり、救急看護認定看護師になりました。
年間の救急車受け入れ台数や緊急入院の患者が多いため、忙しい部署ではありますが、スタッフ皆で協力し合いながら、救急病棟・救急外来で質の高い看護ケアが提供できるよう努めています。とてもやりがいや働き甲斐を感じられる部署です。
2022/1/7
このたび、乳がん看護認定看護師となりましたFです。現在は外来に所属しております。
乳がん患者さんは毎年増加傾向にあります。患者さんは、若年で発症することが多く、社会や家庭での役割を担いながら治療と生活を両立する必要性が出てきます。また、ここ数年で多くの新薬が承認されている事や、最近では遺伝の視点も重要となってきており、専門的な知識が必要とされています。
患者さんご自身が、治療方法を選択する場面が多く、また、長期生存が見込まれる乳がん患者さんへの意思決定支援が看護師には求められています。認定看護師として、診断期から、回復期、終末期まで長期にわたり患者さんの不安に寄り添い、治療の支えとなれるように活動していきたいと考えています。
2022/1/5
初めまして。クリティカルケア認定看護師の佐藤絵美と申します。私は普段、ICU・HCU病棟で働いております。
みなさん、「ICU」や「クリティカル」と聞くと、怖いなとか、ピリピリしているのかなっていうイメージが漠然とあると思います。看護の実際も、治療や検査などが一日の大半を占めるかたちとなりますが、その中でも私たちのできる看護ってたくさんあるんですよ。
患者さんは生命の危機的状態であり、精神的にも身体的にもシビアな状況にありますが、だからこそ、私たちの関わりや、声かけがすぐに患者さんの身体や心に変化としてあらわれます。
患者さんの身体の変化をタイムリーにアセスメントし、生体反応について予測し、状態が悪化しないよう予防したり、悪くなっても最小限に抑えようと日々看護を行っています。
私一人では患者さんの看護にあたることはできません。一人の患者さんをチームで支え、心配なことや不安に思うことはチームで共有し、解決できるよう働きかけます。
ですから、日々働いていてもチームの仲間がお互いを支えているのでとても心強いですし、やりがいを感じる日々を送っています。クリティカルな看護ってすごく楽しいんだよーっていうことを一緒に働くスタッフと共有しながら過ごしています。
どうぞ、これからよろしくお願い致します。
2022/1/4
こんにちは。急性・重症患者看護専門看護師の小松です。
急性・重症患者看護専門看護師は、緊急度や重症度の高い患者さんに対して集中的な看護を提供し、患者さんとご家族の支援、医療スタッフ間の調整などを行い、最善の医療が提供されるよう支援する役割を担っています。
現在私は、ICU・HCUに所属しており、突然の病気の発症や手術などの侵襲的治療を受ける患者さんやご家族に対して、苦痛緩和を図り早期回復に向けた支援を行っています。
また患者さんやご家族に必要なケアが行われるよう多職種との協働を通して調整や、権利擁護のための倫理調整を行っています。
今後は実践の場での研究活動や、部署内外からの相談や教育を通して、より質の高いクリティカルケアを患者さんやご家族に提供できるよう努めていきたいと思います。