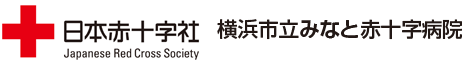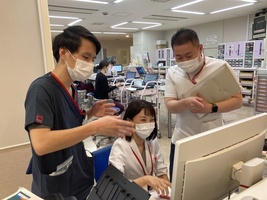切れ目のない医療~チーム医療と地域連携
2024/10/09


今回は、病院と地域医療との連携にかかわる薬剤師についてのお話です。
当院は、救命救急センターを中心とした3次救急(命に関わる重篤な患者さんへの救急医療)と急性期医療を担っています。その一方で、地域がん診療連携拠点病院としてさまざまながんの治療にも取り組んでいます。
ところで、もしあなたが、怪我をしたり体調が悪くなったら、先生(医師)に診てもらって治したいと思うのではないでしょうか?
そのとき、どこの医療機関(クリニックや病院)に行きますか?
昔だったら、直接病院に行っていたかもしれません。でも今は、各病院は、各地域の中でそれぞれ役割が振り分けられています。たとえば当院は、地域のクリニックの先生から紹介された患者さんを治療して地域にお返しするという役割の病院(急性期病院)でもあります。
そもそも「なぜ病気を治したいと思うか」と考えると、「その人らしく日常を過ごせるように」というためではないでしょうか。
病院で治療を受けるというと、「病院に入院し、治療して治って退院」のようなイメージをお持ちかもしれませんが、もし完全には治せない病気だったとしても時には「その病気とうまく付き合いながら生きていく」という選択も患者さんによっては取られる場合もあります。
どちらであってもその方にとって病院は通過点で、日常生活を送る場ではありません。患者さん一人一人が、それぞれの日常に戻るためには、その方が過ごす地域の医療者と病院が連携することが必要です。
そして、医療の担い手として医師、看護師とともに薬剤師も関わっています。
では、病院の薬剤師と地域の保険薬局薬剤師が、患者さんがその人らしい日常生活が送れるようサポートしていくために、どのように連携をしているのでしょう?
たとえば、入院患者さんの場合、退院後も継続して注射薬が必要な場合や入院中に医療用麻薬が開始された場合などでも家で過ごす事はできますが、設備や免許の上で対応できる薬局が限られる場合があります。
その患者さんが退院した後も問題なく薬が使える様に、入院中から退院後の利用薬局を確認して連携しておく必要があります。
退院後の患者さんの療養がうまくいくように、退院前に患者さん宅に退院後往診する医師や看護師、薬剤師等と合同で、患者さんやそのご家族も交えた退院前カンファレンスが開催されることがあり、薬剤師も参加して情報の提供や共有に努めています。
また、外来患者さんの場合、当院では処方箋を発行して院外の薬局でお薬をもらう仕組みになっていますが、一部の治療薬や痛み止めの中には、薬局によっては取り扱っていないものもあり、治療のためにすぐ必要な薬がすぐには受け取れないということがないように、病院薬剤師が間に入って、保険薬局に在庫の確認をするなど患者さんをサポートすることもあります。
もちろん、薬剤師がやることは薬があるかないかという物流のことだけではありません。
地域包括医療のなかで、目の前の患者さんの治療がうまくいくように、患者さんにアドバイスをしたり、患者さんの状態を把握し、薬の効果や副作用を確認して、患者さん側にたって医師に相談や提案をしたりします。
今年、日本緩和医療薬学会の地域緩和ケアネットワーク研修というプログラムで、地域医療を担う薬局の薬剤師さんが当院に研修に来られました。
地域で様々なクリニックの医師と協働し、奔走されていらっしゃるということで、研修最終日に当院薬剤部の部員会で、訪問薬剤管理指導の実際を一部紹介して頂きました。
患者さんがどこにいても切れ目のない医療を提供する為に、病院薬剤師と地域の薬局薬剤師とが相互理解する良い機会となりました。(写真)
医療の進歩、社会の変化、医療制度の改変などに従って、患者さんの選択肢が増えています。私たち薬剤師も、日々変化する医療を支える医療者の一員としてそれぞれの立ち位置で頑張っています。
当院は、救命救急センターを中心とした3次救急(命に関わる重篤な患者さんへの救急医療)と急性期医療を担っています。その一方で、地域がん診療連携拠点病院としてさまざまながんの治療にも取り組んでいます。
ところで、もしあなたが、怪我をしたり体調が悪くなったら、先生(医師)に診てもらって治したいと思うのではないでしょうか?
そのとき、どこの医療機関(クリニックや病院)に行きますか?
昔だったら、直接病院に行っていたかもしれません。でも今は、各病院は、各地域の中でそれぞれ役割が振り分けられています。たとえば当院は、地域のクリニックの先生から紹介された患者さんを治療して地域にお返しするという役割の病院(急性期病院)でもあります。
そもそも「なぜ病気を治したいと思うか」と考えると、「その人らしく日常を過ごせるように」というためではないでしょうか。
病院で治療を受けるというと、「病院に入院し、治療して治って退院」のようなイメージをお持ちかもしれませんが、もし完全には治せない病気だったとしても時には「その病気とうまく付き合いながら生きていく」という選択も患者さんによっては取られる場合もあります。
どちらであってもその方にとって病院は通過点で、日常生活を送る場ではありません。患者さん一人一人が、それぞれの日常に戻るためには、その方が過ごす地域の医療者と病院が連携することが必要です。
そして、医療の担い手として医師、看護師とともに薬剤師も関わっています。
では、病院の薬剤師と地域の保険薬局薬剤師が、患者さんがその人らしい日常生活が送れるようサポートしていくために、どのように連携をしているのでしょう?
たとえば、入院患者さんの場合、退院後も継続して注射薬が必要な場合や入院中に医療用麻薬が開始された場合などでも家で過ごす事はできますが、設備や免許の上で対応できる薬局が限られる場合があります。
その患者さんが退院した後も問題なく薬が使える様に、入院中から退院後の利用薬局を確認して連携しておく必要があります。
退院後の患者さんの療養がうまくいくように、退院前に患者さん宅に退院後往診する医師や看護師、薬剤師等と合同で、患者さんやそのご家族も交えた退院前カンファレンスが開催されることがあり、薬剤師も参加して情報の提供や共有に努めています。
また、外来患者さんの場合、当院では処方箋を発行して院外の薬局でお薬をもらう仕組みになっていますが、一部の治療薬や痛み止めの中には、薬局によっては取り扱っていないものもあり、治療のためにすぐ必要な薬がすぐには受け取れないということがないように、病院薬剤師が間に入って、保険薬局に在庫の確認をするなど患者さんをサポートすることもあります。
もちろん、薬剤師がやることは薬があるかないかという物流のことだけではありません。
地域包括医療のなかで、目の前の患者さんの治療がうまくいくように、患者さんにアドバイスをしたり、患者さんの状態を把握し、薬の効果や副作用を確認して、患者さん側にたって医師に相談や提案をしたりします。
今年、日本緩和医療薬学会の地域緩和ケアネットワーク研修というプログラムで、地域医療を担う薬局の薬剤師さんが当院に研修に来られました。
地域で様々なクリニックの医師と協働し、奔走されていらっしゃるということで、研修最終日に当院薬剤部の部員会で、訪問薬剤管理指導の実際を一部紹介して頂きました。
患者さんがどこにいても切れ目のない医療を提供する為に、病院薬剤師と地域の薬局薬剤師とが相互理解する良い機会となりました。(写真)
医療の進歩、社会の変化、医療制度の改変などに従って、患者さんの選択肢が増えています。私たち薬剤師も、日々変化する医療を支える医療者の一員としてそれぞれの立ち位置で頑張っています。